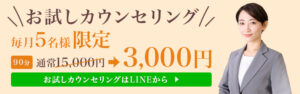先に述べた急性期悲嘆の時期は、混乱した状態のため、自分自身をよく理解したり分析することが難しい時期です。
しかし、やがて悲しみの感情が和らぎ、必要な行動を比較的冷静に行うことができる時期が訪れます。
これが本格的な悲嘆への移行期、つまりショック期と呼ばれる時期です。
この時期は、必要な行動はできるものの、強い緊張感と過敏な状態にあります。
そして、この急性期の反応からショック期を経て、本格的な悲嘆が現れてきます。
悲嘆の心的反応には、①思慕、②疎外感、③うつ的不調、④適応対処の努力の4つがあります。
①から③までは、喪失に関連する「喪失反応」であり、悲しみ、嘆き、故人を追い求める感情的な反応です。
一方、④は「現実への対処」を求める願望で、苦しみながらも何とか生き抜こうとする理性的、現実的な思考や行動反応です。
この悲嘆の期間は、統計的には平均して4年半と言われていますが、亡くなった対象者によって当然異なります。
「悲嘆は生涯続く」とも考えられていますが、
ここでは、これまでの生活とは異なる新しい生き方を身につけ、
何とか一区切りをつけたという意味での悲嘆の終結を指しています。
次回からは、「日本人の4つの悲嘆」について詳しく掘り下げていきたいと思います。